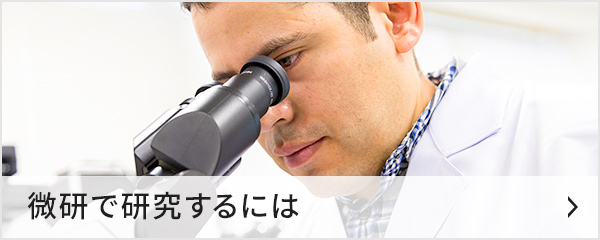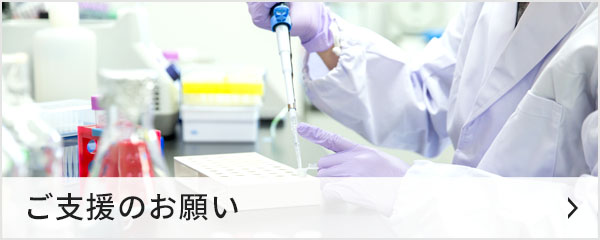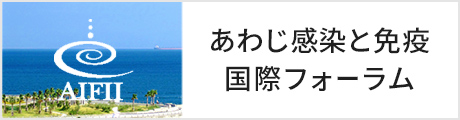感染動物実験施設 概要
感染症や免疫疾患、がんなどでは、病原体や免疫細胞、がん細胞と生体との相互関係により病態が現れます。従って、これらの病態およびその治療法の研究には、病原因子と生体との相互作用を個体レベルで解析することが必要とされます。このためには臨床でのデータの蓄積のみならず、適切な代替実験方法がない場合には、動物実験による解析と検証は不可避のものとなります。大阪大学微生物病研究所では、疾患研究における動物実験の重要性を認識するとともに、それらの実験を安全かつ適正に行うため、1967年に感染動物実験施設を設立しました。以降、時代に即応した運営を目指しつつ、生命科学研究において大きな役割を担い続け、今日に至っています。
施設には、感染実験対応の両面型高圧蒸気滅菌器、HEPAフィルターを介した給排気装置、24時間対応の空調設備を備えており、ABSL2の感染動物の飼育と実験が安全に行える設備が整っています。また、2023年には感染症共同実験施設が新設され、共同でABSL3の動物実験設備を運用しています。実際の施設使用にあたっては、①教育訓練、②動物実験計画書の提出と審査、③定期的な微生物学的モニタリング、④年次報告等により、適正な動物の飼育と実験が行われるよう努めています。近年は、動物実験の基準理念である3R(Replacement,Reduction,Refinement)に加え、動物の5つの自由にも配慮した環境を整えています。
また、遺伝子情報解析分野と共同し、ゲノム編集や生殖工学・発生工学を基盤とした遺伝子組み換え動物作製技術の研究・開発を行うとともに、①トランスジェニック動物の作製、②ノックアウト・ノックイン動物の作製、③顕微授精による系統維持、④動物系統の凍結保存など、最先端の生殖工学・発生工学技術を用いた動物実験のための研究支援を行っています。(表1)
| IVF/ET | TG | KO, KI | |
|---|---|---|---|
|
2000まで |
261 | 228 | 50 |
| 2001-2003 | 443 | 104 | 57 |
| 2004-2006 | 331 | 43 | 69 |
| 2007-2009 | 216 | 22 | 74 |
| 2010-2012 | 388 | 55 | 152 |
| 2013-2015 | 580 | 50 | 242※ |
| 2016-2018 | 505 | 21 | 191※ |
| 2019-2021 |
702 (移植246,凍結保存456) |
44 | 466※ |
| 2022 |
312 (移植52,凍結保存260) |
14 | 156※ |
| 2023 |
209 (移植52,凍結保存157) |
16 | 116※ |
| 2024 |
233 (移植 55,凍結保存 178) |
15 | 135※ |
表1 施設において作製・保存されたマウスの系統数
IVF: In vitro fertilization(体外受精)、ET: Embryo Transfer(胚移植)、Tg: Transgenic(遺伝子組み換え動物)、KO, KI: Knock out, Knock in(ノックアウト、ノックイン)
※CRISPR-Cas9 などのゲノム編集技術を用いて作製した遺伝子改変マウスを含む
メンバー
- 施設長: 伊川 正人 教授
- 准教授: 宮田 治彦(兼)
- 特任准教授: 北本 宗子(兼)
- 助教:江森 千紘(兼)
- 助教:増子 大輔
- 助教:畑中 勇輝
- 特任助教: 飯田 理恵(兼)
- 特任助教: 藤内 慎梧(兼)