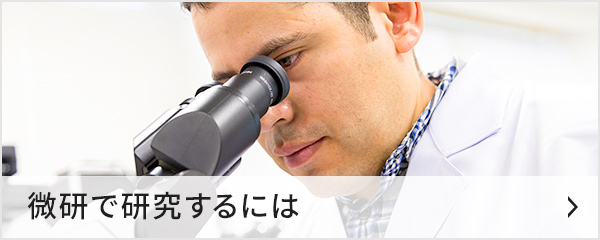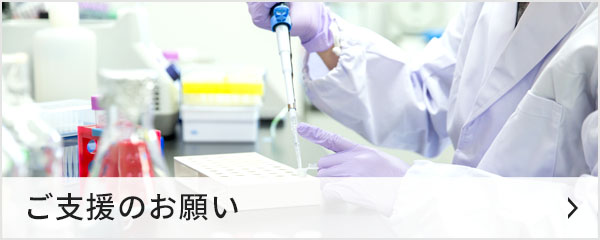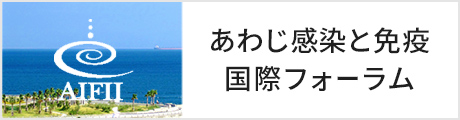ノーベル賞テーマ「制御性T細胞」研究の広がり
2025年10月7日
新着情報
微研から生まれる、新しい免疫制御の可能性
2025年のノーベル生理学・医学賞は、「制御性T細胞(Regulatory T cell, Treg)」の発見とその免疫抑制機構の解明に対して授与されました。
Tregは、免疫反応を適切に抑える“ブレーキ役”として、免疫の恒常性を保つうえで欠かせない存在です。
その働きの異常は、自己免疫疾患・がん・感染症・アレルギー・臓器移植の拒絶反応など、多様な病態の発症や進行に深く関与していることが知られています。
この発見は、免疫系のバランスを理解する上での転換点となり、医療応用にも大きな道を開きました。
微生物病研究所では、このTreg研究の流れを受け、「免疫のバランスをどのように精密に制御できるか」という課題に挑む研究が進められています。
以下の3つの研究成果は、Tregの働きを“抑える”あるいは“支える”という両側面から捉え、免疫系をより柔軟に制御する次世代の基礎研究として注目されています。
1.自己免疫を起こさずにがん免疫を誘導する新しい仕組みを解明 ― 制御性T細胞の一部を選択的に除去
山本雅裕教授らの研究グループは、特定の免疫細胞を任意に除去できるマウス(VeDTRマウス)を開発し、Tregの一部であるTh1型Tregだけを選択的に除去することに成功しました。
その結果、自己免疫炎症を引き起こすことなく、強力ながん免疫応答を誘導できることを明らかにしました。
この成果は、「免疫のブレーキを部分的に外す」ことで副作用を抑えつつ、がん治療効果を高める新しい免疫療法の基盤となる可能性を示しています。
2.自己免疫疾患の炎症を抑える仕組みを発見 ― 制御性T細胞が免疫の暴走を防ぐ
多発性硬化症の動物モデル(EAE)を用いた解析により、IFN-γ刺激を受けたTregがTh1型Tregへと分化し、炎症部位で神経損傷を抑制することが確認されました。
この知見は、Tregの多様性と可塑性を示すものであり、疾患の種類や局所環境に応じてTregが異なる役割を果たすことを明らかにしています。
自己免疫疾患治療の新たな標的細胞として、Th1型Tregが注目されています。
3.がんの免疫を抑える仕組みを発見 ― 血小板由来の分子PF4がカギ
腫瘍随伴マクロファージ(TAM)が分泌する血小板因子PF4が、Th1型Tregを誘導し免疫抑制を引き起こす仕組みを解明しました。
PF4を中和することでTh1型Tregの誘導が抑えられ、腫瘍内の免疫反応が活性化し、腫瘍増殖を抑えることができました。
この経路を標的とすることで、自己免疫を誘発せずに腫瘍免疫を高める新たな治療法開発が期待されます。
<こちらあわせてもどうぞ>
上記研究を展開する山本雅裕教授のインタビュー
山本雅裕教授に聞く「Th1型制御性T細胞の除去は安全にがん免疫を誘導する」
- ホーム
- NEWS&TOPICS